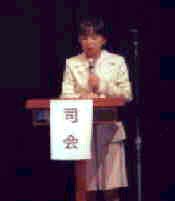
須賀春美さん
| 司会 | 須賀 春美 | (東腎協青年部幹事) |
| 1.主催者あいさつ | 糸賀 久夫 | (東腎協会長) |
| 中西 好子 | (東京都衛生局参事) | |
| 2.講演 | (1)「蛋白尿が出ていると言われたら」 | |
| 飯野 靖彦先生 | (日本医科大学第二内科教授) | |
| (2)「透析導入と言われたら」 | ||
| 篠田 俊雄先生 | (社会保険中央総合病院腎臓内科部長) | |
| 3.パネルディスカッション | ||
| 「腎臓病の体験談」、会場からの質問 | ||
| パネラー | 飯野 靖彦 先生 | (日本医科大学第二内科教授) |
| 篠田 俊雄 先生 | (社会保険中央総合病院腎臓内科部長) | |
| 野口 和 氏 | (慢性糸珠体腎炎患者) | |
| 山崎 理奈 さん | (糖尿病性腎症保存期の患者) | |
| 司 会 | 一ノ清 明 氏 | (東腎協副会長 虎の門・高津会会員) |
| 日 時 | 平成14年(2002年)2月4日(日) | 午後1時〜4時 |
| 場 所 | 豊島区民センター文化ホール(定員279人) | |
| 主 催 | 東京都腎臓病患者連絡協議会 | |
| 東京都 (社)日本腎臓学会 | ||
| 後 援 | 豊島区、北区、練馬区、(社)東京都医師会、(社)日本透析医学会、(社)日本透析医会、 (社)日本臓器移植ネットワーク、三多摩腎疾患治療医会、東京難病団体連絡協議会 ライオンズクラブ国際協会330−A地区、、(財)日本腎臓財団、(社)全国腎臓病協議会 |
|
| 主催者あいさつ |
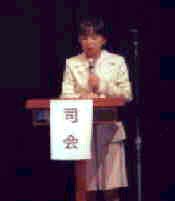 |
| 虎の門・高津会会員 須賀春美さん |
司会 私は主催者である東京都腎臓病患者連絡協議会の青年部で幹事をしております須賀と申します。
学生時代に透析を始めまして、ことしで25年になります。現在は夜間透析を受けながら会社員として社会復帰をしております。
それでは、主催者である東京都腎臓病患者連絡協議会の糸賀会長よりごあいさつ申し上げます。(拍手)
東京都腎臓病患者連絡協議会
会長 糸賀 久夫
私たち東腎協は、腎臓病の末期になって、透析をしながら生活をしている患者の団体です。会員は現在7千人ほどおります。
昨年、透析患者は、20万人台を突破し、東京都内では、その1割の20、422人が透析をしているということです。全国的に見ますと非常に残念ながら9千人ぐらいずつ、増えています。
僭越ですけど、ここで私の腎臓病との出会いを少しお話しさせていただきたいと思います。私が腎臓病とわかったのは、今から30年前の昭和47年の6月でした。
「あなたの腎臓は6%しか働いていません」と腎不全を宣告され、その年の12月から透析導入ということになりました。
ちょうど23歳のときですけども、当時は何で早く医者に行かなかったのかと後悔の連続で、自分の腎臓で生きられない、大変ショックなわけですよね。若い人であればあるほどショックなり絶望感が大きいと思います。
このときほど健康のありがたさ、検診とか検尿あるいは早期発見、早期治療などの大切さを痛感したことはありません。
 |
| 東腎協会長 糸賀久夫さん |
その当時は、私のように病気を発してすぐに透析という例が大変多かったように記憶してお
ります。 現在は検診制度が充 実してますので、検診をきちっと受ければそんなに悪化させ
るということがなく済むだろうと思うんですけども、相変わらず 透析の患者さんはふえ続けて
ます。
日本は検診制度は世界でも整っている方だと思うんですね。ですから、この検診制度をき ちっと生かしていくということが 大事だろうと思うんです。
制度は整ってますけれども、それを本当に生かすのは人間ですから、腎臓病と言われまし たらぜひきちんと病気と向き合ってもらうというようなことが大切なことだと思っております。
病気になった人が一番健康のありがたさがわかるんですけれども、私たちのように取り返し のつかない病気になってしまっては元も子もありません。
私たち、透析の患者の会は当事者として、都民の皆さんにぜひ腎臓病の大切さを訴える役
割も、自らが負ってるだろうと考えております。
透析はご存じのように一度始めますと、移植をしない限り一生続けなければなりません。こ
のような苦しみは私たちだけで終わりにしたいというような思いから、今日のような集いを開
かしていただいております。本日の集いで腎臓病に対する正しい知識を少しでも深めていただけたら大変うれしく思います。
司会 それでは同じく主催者である東京都衛生局、中西参事にごあいさつをしていただきます。
東京都衛生局
参事 中西 好子
本日は多数の皆様のご出席のもとに東腎協と東京都の共催で「腎臓病を考える都民の集い」が、ここ豊島区民センターで開催できますこと大変うれしく思っております。
特に患者会のお立場で同じ病気で苦しんでおられる方々のために、また腎臓病の予防のために、日々ご尽力をされている東腎協の役員や、関係者の皆様におかれましては本当にご苦労様でございます。今回のこの集いも中心的になって企画推進していただきましたこと、まことに感謝申し上げます。
私どもの医療費助成を申請される方々を見ますと、糖尿病で腎不全になられる方が非常に多くなっておられるという現状がございます。
衛生局では東京都単独で人工透析を必要とする腎不全に対する医療費や、また多発性嚢胞腎、ネフローゼ症候群など、国疾病ではないんですけども、東京都で難病と指定をして医療費助成をしております。
また腎臓病の移植希望者に対する組織適合性の検査費助成を初めとしまして、腎疾患の早期発見を図る検診や糖尿病を含めた生活習慣病の予防対策を実施し、健康の保持増進から発病予防、早期発見、早期治療まで、総合的な施策を推進しているところでございます。
これも施策としてはあるのですけれども、都民の皆様が知らないとか、知っているけど検診を受けないとか、さまざまなことがありますので、どうぞ皆様のご協力、またいろいろなことを周知していただければと思っております。
 |
| 東京都衛生局参事 中西好子さん |
また平成13年4月から私どもの東京都衛生局特殊疾病対策課(現健康局医療サービス部疾病対策課)のホームページ
を立ち上げまして、人工透析を受けておられる方への情報を公開しております。
昨年末に改訂しました「災害時における透析医療活動マニュアル」の患者さん向けに書かれた、「透析患者用防災の手引き」や、また都内の「透析対応医療機関名簿」を公表しておりますので、ぜひご活用のほどお願い申し上げます。
それから慢性腎不全に対する根治療法として、既に腎移植が確立しておりますけども、脳死からの臓器移植は、まだ18例にとどまっておりますし、献腎移植の方が近年逆に減少傾向にあるということを非常に憂えております。
移植希望の方が非常に多い中で、期待に応えられないことにつきましては、何とか打開しなければいけないと思っております。
こういった中で、毎年10月を臓器移植の普及推進月間と定めておりますが、東腎協の方も一生懸命取り組んでいただきまして、私どもと一緒にそのキャンペーンとして臓器提供の意思表示カード(ドナーカード)の配布を行っております。私どもとしても区市町村、保健所などへ同カードの設置を勧めているところです。
本日、ご来場の皆様におかれましても、この機会をかりまして今後そのドナーカードの普及啓発をぜひお願いしたいと思っております。
最後に、この集いが本日ご参加いただいた皆様に実り多いものになることを祈念しまして、私のあいさつとさせていただきます。(拍手)
<医療相談に協力していただいた先生>
 |
 |
| 日本医科大学第二内科 藤田有子先生(左) | 日本医科大学第二内科 柏木哲也先生(右) |
東腎協 2003年2月3日 号外
最終更新日 2003年3月20日
作成:K.Atari