![]()
| 今後の活動予定 |
| 6月7日(月) JPC国会請願 7月31日~8月1日 関東ブロック青年交流会 8月28日~29日 全腎協青年交流会 9月26日 第53回幹事会 10月3日 臓器移植推進キャンペーン |
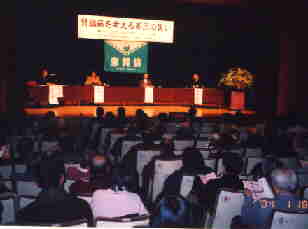 |
 |
| 1月18日「腎臓病を考える都民の集い」 | 2月1日「東部ブロック交流会」 |
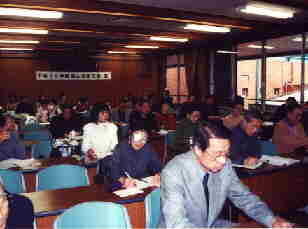 |
 |
| 2月29日「個人会員交流会」 | 3月4日「臓移連国会請願」 |
 |
 |
| 3月21日「第52回幹事会」 | 3月25日「全腎協国会請願」八代議員秘書に |
30余年前は「金の切れ目が生命の切れ目」だった
今は、医療費の心配も余りなく透析医療にかかれる時代ですが、まだ患者会―全腎協―がなかった時代には、「金の切れ目が生命の切れ目」でした。
その当時の患者たちが集まり、生命をかけて運動したことによって築きあげてきたものです。
会員皆さんが、悲惨な状況に置かれていたということを知っていただくために、以下の文章を再録してみました。
「金の切れ目が生命の切れ目」
人工腎臓の医療費が一九六七年(昭和四二年)医療保険の対象となり、患者がそれまでの学用患者、あるいは高額な全額自己負担という経済的精神的呪縛から解放された。とはいっても、それは社会保険(健康保険、共済組合保険など)本人だけのことであった。
社会保険の家族は当時、五割給付であったから五割の患者負担が、国民健康保険の加入者は七割給付であったから三割の患者負担がそれぞれ必要であった。
全腎協結成前の関東地方のある病院の調べ(一九七一年三月分レセプト)による自己負担のある患者八人の事例でみると、最高額の患者は二二万三〇〇〇円余り、最低の患者でも八万六〇〇〇円余り(医療保護受給者を除く)を支払っていた。保険外負担を含めると三〇万円前後の支払いをしていた患者もあった。八人の患者の平均は一一万四〇〇〇円近くで、年間一三六万円にものぼった。一般サラリーマンの平均月収が約一〇万円、大企業の大卒者の初任給が四万五〇〇〇円で話題になった頃の話であった。
医療保険の対象とされていたにもかかわらず、まさに「金の切れ目が生命の切れ目」であると同時に、「保険の切れ目が生命の切れ目」の実態であった。
家屋敷を売り土地を売り、退職金を前借りして家族の医療費に充てる事例もまれではなかった。売る家や土地のある患者・家族、退職金を前借りできる患者・家族はまだ”幸せ”であった。長期に高額な医療費を払い続ける家族に迷惑をかけるからと自殺する患者もいた。生活保護を受給するための方便として離婚する事例もあった。サラリーマンである透析患者が止むなく病気のために退職すればそれは、一〇割給付から七割、五割の給付である国保、健保家族への”転落”を意味した。
全腎協が結成された翌年、激しい運動の結果として身体障害者福祉法にもとづく更生医療が適用された。医療保険の自己負担分を公費(国と都道府県負担)で肩代わりしようというものであった。全腎協が結成時に掲げた要求である「全額国庫負担」ではなく、保険優先の公費医療制度であり、前年度の所得税額により「費用徴収」されるという制約のある制度の適用ではあったが、一〇万円から三〇万円もの自己負担は基本的に解消され、性差、貧富の差、年齢の差なくだれでもいつでも透析が受けられる条件が確立された。 (全腎協の20年「歩みとどまらず」37~38ページ抜粋)
1971年(昭和46年)3月分の人工透析の個人負担額例 関東地方病院
| 性別 | 年齢 | 透析年月日 | 保険負担率 | 負担金額 |
| A 女 | 51 | S 45.11 | 50% | 123,155 |
| B 女 | 52 | 45.11 | 50% | 86,325 |
| C 女 | 49 | 45. 7 | 50% | 120,175 |
| D 男 | 14 | 45. 6 | 50% | 105,391 |
| E 男 | 13 | 45. 4 | 50% | 141,153 |
| F 男 | 33 | 45. 8 | 30% | 101,281 |
| G 女 | 33 | 46. 3 | 30% | 223,520 |
| H 男 | 26 | 44. 2 | 50%(医療保護自己負担) | 10,750 |
| 平均113,939 |
最終更新日:2004年7月20日
作成:K.Atari