![]()
ボタンホール穿刺を……
個人会員(北里研究所透析室)
朝日 美保
全腎協の機関誌で見て、ボタンホール穿刺(いつも同じ場所に針がさせるように、皮膚に穴を開けること。ピアスの穴みたいなもの)を施設にできるか聞いてみました。
| 写真1 ステック |
いつの間にか施設サイドも勉強をしていたようで、ボタンホール穿刺の説明を受け、キットがそろったところでやってみることにしました。平成15年1月21日、ボタンホール穿刺を作るための第一段階をしました。
いつものように透析が終わって、針を抜き止血したら、そこの針穴にピアスのような、透明のスティックを入れます(写真1)。ホールに入れたピンキャップの上に、いつも貼るテープを貼り、さらに防水テープを貼りました。
次の透析のときは、ピンを取り、そこに先の丸い針を入れます(写真2)。まだボタンホール穿刺に慣れていないスタッフたちは、手間取りながらの穿刺でした。
ボタンホールの穿刺は、最初にホールを作った人がしばらくの間(ホールが安定するまで)は、穿刺をしたほうがいいようです。毎回穿刺する人が代わると、ホールでないところに針を進めていってしまうようです。
| 写真2 左:先の丸い針 |
透析が終わってホールがふさがらないようにピンを入れるのは、一週間くらいで、そのあとはもうピンは入れないで、自然にできるかさぶたがピン代わりになります。そして次の透析のときは、かさぶたをきれいにはがすとホールがあるので、そこに針を入れていくといった具合です。
痛みは普通の穿刺よりもかなり軽減されていて、今までは、血管が細くて穿刺に苦労していたので、今はとても快適です。また、穿刺の痕がたくさん付かないのも嬉しいです。ボタンホールのキットはニプロのものを使用しています。
現在、北里研究所では火・木・土で、4人(火・木・土の外来透析は5人)ボタンホールを実施しています。血管に沿った穿刺の痕が消えて、きれいな腕になった患者も出てきています。
国の財政危機と患者会の活動について
虎の門・高津会 事務局長
大場 光伴
平成14年2月14日の第154国会で、非常に気になる質疑が交わされています。それは、前年に一部関係者や政治家に渡ったまるひレポート「ネバダレポート」を取り上げて、当時の柳沢財務大臣、竹中経済財政担当大臣に、五十嵐議員が質問したものです。
「ネバダレポート」とは、日本の赤字がいかに深刻であるかを指摘したものです。柳沢金融再生担当大臣(当時)が、IMFによる日本の金融セクターの審査受け入れを明言。IMFが日本経済再生に乗り出す場合、8項目の施策をとる可能性を列挙しています。すでに今年の春、日本はIMFの審査を終えたようです。
さて、現在の医療費助成制度が廃止され、一般の保険と同じように、1割〜3割負担になれば、透析者はかなり高額負担を強いられ、31年以上前の悪夢「金の切れ目が命の切れ目」が蘇ります。
さらに消費税のアップ、預金からの徴収、年金のカットと追い討ちをかけられればなお更です。現在でも病院食の費用が患者負担になり、病院食を止め、お弁当を持参して透析する患者さんが増えるなか、これ以上の負担は患者会として必ず阻止しなければならない重要な問題です。
3年ほど前から公共事業費より医療費は多くなり30兆円を大きく超えていて、一方公共事業費は20兆円台後半まで落ちています。合計すると約60兆円が使われている勘定になります。
「団塊の世代」と言われる約800万人の世代の人々は、今まで原動力になっていましたが、高齢化を迎え3年以上先には逆に年金受給者となり、払う側から支給される側になるのです。少子化が進むなか税収は少なくなり、支出が増えれば、私たちの医療費も将来財政危機と共にますます削減を余儀なくされます。
30年以上前に先人の透析患者が医療費助成制度のため立ち上がったように、透析治療を受けなければ命がない私たちは、再び一致団結して、この非常事態を乗り越えて行かなければならないのです。
透析患者は精神的にも肉体的にも不安を持ちながら透析治療を受けています。患者会がなぜ必要なのか、もう一度患者会創立期の原点に立ち返り、患者会の意味を透析患者は知る必要があるのではないでしょうか。
今までのような体制を維持できて治療ができると思い、「誰かがやるだろう」と患者会に入会せず活動にも参加しないといった考え方では、透析治療の将来はないと言っても過言ではない状況なのです。
現在、我々が思う以上に事態は深刻な状況に近づいていることをご理解していただき、今後の医療保障制度と患者会の活動に関心を深めて頂きたいと思います。
全腎協関東ブロック青年交流会に参加して
豊生会 秋山 伸子
晴天に恵まれた9月13日・14日の両日、群馬県の猿ヶ京温泉で開催された「全腎協関東ブロック青年交流会」に初めて参加しました。
 |
| 左から秋山さん、小関青年部長 須賀副部長 |
当日は東腎協から参加した3名を含む関東1都6県、48人の青年部会員が集まり、開会後、日高病院管理栄養士 中山優子先生の講演「健康は元気と透析の調和から」を拝聴し、その中で「自己管理と5年後の目標を持つ事の大切さ」を教えていただきました。
テーマ別グループ討論では、「青年部の活動状況について」「食事のコントロール」「移植状況」の3つのテーマをそれぞれのグループで話し合いました。その後夕食を兼ねての交流会では短時間でしたが、他県の皆さんの貴重なご意見を聞くことができ、楽しい時間を過ごす事ができました。
今回この交流会に参加できたことでこれまで狭い中での見識しかなかった私にとって数多くの目新しい情報や勇気をたくさん頂き、今後透析患者として生活していく上で大事なもののひとつを得ることが出来たと感じながら帰路につきました。
これまでも自分なりに努力をしてきたつもりですが、より一層日々の節制と努力を積み重ね(…といってもあまりストレスにならない程度の話ですが…)5年後の目標に向かってこれからも頑張りたいと思います。
あけぼの友の会日帰りバス旅行に参加して
編集部
 |
| 全員集合 |
平成15年9月7日。参加者60名、病院から医師2名、看護師長1名看護師1名が参加されていた。
久里浜から金谷までフェリーに乗船。鋸山のロープウェイの展望台から360度の眺めを堪能して、昼食は近くの旅館へ。ドジョウの柳川なべなど美味しく頂く。ビンゴゲームで盛り上がり、さらにカラオケで大宴会♪ 帰路は干物屋と海ほたるで、皆さん楽しそうにお土産を買っていた。
今回のバス旅行では役員の事前の準備の良さがうかがえ参加の会員も楽しそうでした。
腰の手術日記 その2
にこたま会
押山 大作
(その1はNo.148号。術後1週間のベッド上安静に入る)
手術翌朝(木曜日)腰の奥はズンと痛い。朝食は食べやすいように、おにぎりにしてもらう。食欲なし。午前中さっそく、術衣からパジャマへ着替えと清拭。
右へ、左へ身体をごろごろ回転させて、完了。上半身と下半身を同調させて寝返るのは難しい。「これもリハビリです」だって。「へぇー」。しかし、着替えて気持ちがすこしさっぱりする。術後のレントゲン写真を見て、大工仕事のような手術を想像。身震いする。
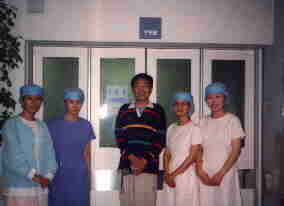 |
| 手術室スタッフと |
起きられないので、手が届かないところの物は、おもちゃのマジックハンドが役に立つ。ベッドの柵にはポケットをつけてもらい、薬など入れておく。1日が長い。
手術後2日目。透析室へは病室のベッドごと移動。体重は、寝たまま担架のようなものに移り、それを吊るして計る。空中浮遊? 透析室スタッフは術後の患者に慣れていて、心配りが行き届いている。やはり痛みが辛く、時間を短縮。
土曜日。ベッドに寝たままで、洗髪をしてもらう。気持ちいい。食事のとき上体を30度起こす。以後45度、60度と上げていく。
トイレを心配していたが、とうとう下剤服用。結果、ベッド上で看護師の世話になる。赤ちゃん状態! 痛みはかなり減り、点滴から内服に変わった。しかしまだ仰向けは痛い。
術後1週間。辛かったベッド上の安静を乗りきった。コルセットをしてゆっくり立ち、歩行器を試してみる。立てた、歩けた。
嬉しい。腰も伸びている。やったー。部屋の中を歩行器で歩き回って、喜びを実感する。自分でトイレにいけるのも本当に嬉しい。歩行のリハビリが始まる。まだ、腰をひねるのは厳禁だが気を抜くと危ない。前かがみも怖くて出来ず。
安静解除になったら、すぐシャワー許可も出た。防水絆創膏を貼って、着替えから身体を洗うことまで、看護師に介助してもらう。生き返ったような爽快感!
抜糸は慎重を期して、2週間を過ぎて半抜糸。3週間で全抜糸。キレイに傷口は付いていた。抜糸したとたん、退院の許可が出る。退院前に私の手術を担当してくれた手術室の看護師には全員そろってお会いできた。杖をついているが、歩いて退院するところを見てもらえて良かった。
三上先生、高橋先生、乳原先生、病棟、透析室のスタッフの皆さん、ありがとうございました。
腰の具合が悪いときに比べ、気持ちが前向きになり、意欲も湧いてきた。手術の決断には時間がかったが、受けて本当に良かった。
短歌
「想い出」
山田クリニック腎友会 水上 清吾(80歳)
寄り添いて 言葉少なに ただ歩む
アカシヤ並木 木漏れ日の道
あたたかき 君が手にふれ 吾が胸の
ときめきやまず その夜眠れず
夢に見る 今亡き君は 知りそめし
二十(はた)とせのまま 吾に微笑む
俳句
武蔵境駅前クリニック腎友会 荻原 た可司(85歳)
何日迄と 問はる 透析 夕端居
病葉の 風なく音のなく散れり
おとぼけも 堂に入りたる 生身魂
|
東腎協のメールアドレスが変わりました。新アドレス info@toujn.jp |
最終作成日:2003年12月23日
作成者:K.Atari